相続した実家が「空き家」だったときに直面する問題とは?
実家の相続は人生でそう何度も経験することではありません。そのため、突然訪れた空き家の相続にどう対応すべきか分からず、悩む方が後を絶ちません。
空き家には、維持コストや近隣トラブル、流動性の低さなど、さまざまなリスクが存在します。とくに郊外や過疎地域にある空き家は「売ろうと思っても売れない」ケースが多く、対策を講じないまま放置すると、資産どころか負債にもなりかねません。
売却できない「負動産」化の典型事例
実際にあったご相談では、関東近県の築40年を超えた空き家が問題となりました。この物件は駅から遠く、歩いてアクセスできる距離ではありません。建物は老朽化し、住居として再利用できる状態ではなく、年間5万円前後の固定資産税が発生していました。
さらに、土地の種別が農地のままになっていたため、一般的な住宅用地と異なり、売却には農地転用の許可が必要で、農家以外への売却が困難でした。こうした法的制限がネックになり、相場通りの査定価格(800万円)では売れる見込みがない状況でした。
極めつけは、台風によって屋根の一部が剥がれ、隣家の室外機を破損するというトラブルまで発生。所有者は修理費を負担することになり、所有し続けるだけでも金銭的なリスクがあることが明らかになりました。
空き家が売れない理由は「立地」「状態」「法規制」
空き家の売却が難しい主な原因は、次の3点に集約されます。
立地条件が悪く需要がない
郊外や山間部など、人口減少が進むエリアでは不動産の需要自体が低く、周辺に新築住宅や商業施設がない地域では、買い手が見つかりません。
建物の状態が悪く再利用が難しい
古い木造住宅であれば、耐震性や雨漏りの問題からリフォーム費用がかさみ、購入希望者の負担が大きくなります。その結果、物件の評価が著しく下がります。
農地や市街化調整区域など法規制の対象である
土地が「畑」や「山林」になっている場合、農地法の制限により転用許可が必要です。都市計画法による市街化調整区域であれば、建築の可否や開発行為に制限があるため、一般向けに売却することが困難です。
空き家の放置がもたらす5つのリスク
相続した空き家を放置してしまうと、次のようなリスクが生じます。
- 固定資産税などの維持コストが毎年発生する
- 老朽化により倒壊や破損、近隣への損害リスクが増す
- 放火や不法投棄など、治安上の問題が起きやすくなる
- 2024年施行の法改正により「管理不全空き家」として認定される可能性
- 相続登記義務化により、名義変更を怠ると過料が発生する
とくに、2024年4月に義務化された相続登記を怠ると、最大で10万円の過料が科される可能性があるため、手続きの放置はリスクを高めます。
まず検討すべき「売却」の選択肢
空き家の出口戦略としてもっとも現実的なのが売却です。ただし、「売れる物件」と「売れない物件」があることを前提に、具体的な選択肢を見ていきましょう。
不動産会社に仲介依頼する
相場に近い価格で売りたい場合は、地域の不動産会社に売却を依頼するのが基本です。ただし、流通性の低いエリアでは売却までに時間がかかるため、早期売却を希望する場合には不向きかもしれません。
不動産買取業者に直接売却する
売却価格は相場よりも低くなる傾向がありますが、条件によっては即現金化が可能です。築古住宅や農地、管理困難な空き家は、買取の選択肢を持つことで機会を広げられます。
解体して更地にする
老朽化が進んだ住宅であれば、建物を解体して更地にすることで、売却しやすくなるケースもあります。ただし、解体費用は一般的に100万~200万円程度かかるため、慎重な費用対効果の検討が必要です。
空き家バンクや支援制度を活用する方法
自治体では、空き家の流通促進を目的として「空き家バンク」を設置しています。これは、空き家を所有している人と、空き家を活用したい人をマッチングする仕組みです。
空き家バンクのメリット
- 購入希望者との接点が得られる
- リフォーム補助金などの制度と連動しているケースが多い
- 売却以外に、賃貸や事業利用としての提案も可能
空き家バンクは全国の自治体で運用されていますが、「活用意欲のある人」が見つかりにくいため、掲載したからといってすぐに結果が出るとは限りません。あくまで手段のひとつとして、他の方法と並行して活用するのが現実的です。
解体して「貸し農地」や「駐車場」にする方法
売却が困難な場合は、土地の形を変えることで収益化を図る方法もあります。たとえば、農地であれば自治体の「農地バンク」を通じて貸し出す、または、都市計画区域内であれば月極駐車場として利用するなどです。
貸し農地として登録すれば、収益性は小さくとも維持コストを軽減できます。駐車場に転用する場合、舗装や整備が必要ですが、周辺に月極駐車場が少ないエリアであれば需要を見込める場合もあります。
2024年〜2025年にかけての制度改正と注意点
空き家の相続と売却において、無視できないのが法改正の影響です。とくに2024年以降、2つの重要な制度改正が空き家対策に影響を及ぼしています。
相続登記の義務化(2024年4月〜)
これまでは任意だった相続登記が、2024年4月から義務化されました。これにより、相続によって不動産を取得した場合、3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
登記を怠ったままでは売却も活用もできず、さらに放置されることで、次の相続人への負担が増大してしまいます。名義変更が済んでいない場合は、早急に対応しましょう。
空き家対策特措法の改正(2023年12月〜施行開始)
従来は「特定空き家」に対して固定資産税の軽減措置が外される措置がありましたが、改正後は「管理不全空き家」も対象になりました。これにより、放置状態にある空き家が行政指導の対象となり、修繕・解体の命令が出る可能性が高まりました。
特に「草木が生い茂っている」「建物の傾きが目立つ」といった状況では、個別に現地調査を受けるリスクがあるため、早めの対処が求められます。
再生事例:誰も住まない家を資産に変える工夫
実家の空き家が完全に需要のない物件であっても、創意工夫によって新たな価値を生み出すことが可能です。いくつかの事例をご紹介します。
解体後に月極駐車場として収益化
ある郊外の住宅地では、家屋の解体後にアスファルト舗装を行い、2台分の駐車場として月額8,000円で貸し出したケースがあります。初期投資は100万円程度でしたが、10年で回収可能な見込みとなり、放置よりもはるかに有益でした。
アーティスト向けのシェアアトリエに転用
また別の事例では、築50年の空き家を簡易的にリフォームし、地元のアーティスト向けの工房兼展示スペースにした事例もあります。SNSで情報発信を行い、クラウドファンディングで運営資金を確保したことで、地域に新たな文化スポットとして注目されました。
こうした活用には、地域コミュニティとの連携が不可欠ですが、「売れないから終わり」ではなく「価値を変換する」という視点が大切です。
久喜市周辺における事例と対応の提案
フジハウジングが拠点とする埼玉県久喜市周辺でも、相続空き家の相談は増加しています。特に加須・羽生・幸手などの農地混在地域では、売却だけでなく、「農地転用」を通じた活用ケースが増えています。
当社でも、不動産相続に関する相談を受け付けており、希望条件のヒアリングから専門的な提案まで、ワンストップで対応しています。
初めての相続でお困りの方は、どうぞ気軽にご相談ください。
まとめ:空き家相続で損しないために
空き家の相続は、放置すると資産価値を大きく毀損する可能性があります。しかし、売却・活用・支援制度の活用など、視点を変えることで出口戦略は見えてきます。
とくに2024年以降の法改正により、早めの対応が強く求められています。
「売れない」と諦めるのではなく、「どう活かすか」を考えることが、空き家問題を乗り越える鍵となります。
フジハウジングでは、こうした空き家の相続・売却・活用について、多くの事例とノウハウを持っています。実家の空き家でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
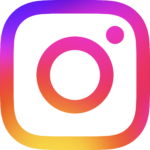
知って楽しい久喜 公式Instagram
久喜のタウン情報発信中!
地域の魅力をお届けしています!
【知って楽しい久喜】すまいの相談窓口infoとは
久喜市の不動産会社 株式会社フジハウジングが運営する、不動産解決事例や久喜の情報を発信しているタウンメディアです。
フジハウジングでは、お客様のニーズに合わせたご提案を行い、不動産を通じた人生設計を応援しています。
賃貸物件のお探し・賃貸管理・資産価値リフォーム・おうち探し・土地探し・不動産のご売却・不動産相続対策・有効活用など、トータルに解決出来るプロ集団ですので、是非お気軽にご相談ください









