不動産の減価償却、計算手順や仕組みを解説。節税メリットも!
不動産には「減価償却できる資産」と「減価償却できない資産」があることをご存じでしょうか?
減価償却とは、建物や設備などの資産を使用年数に応じて少しずつ費用として計上する会計上の処理方法であり、不動産の取得や運用においてとても重要です。
特に、減価償却が可能な建物では、適切に計上することで大きな節税効果を得ることができます。
一方で、土地は減価償却の対象外であり、建物と土地を正しく区分する必要があります。
本記事では、不動産における減価償却の基本的な仕組みや計算方法、節税効果の活用例、そして注意すべきポイントについてわかりやすく解説していきます。
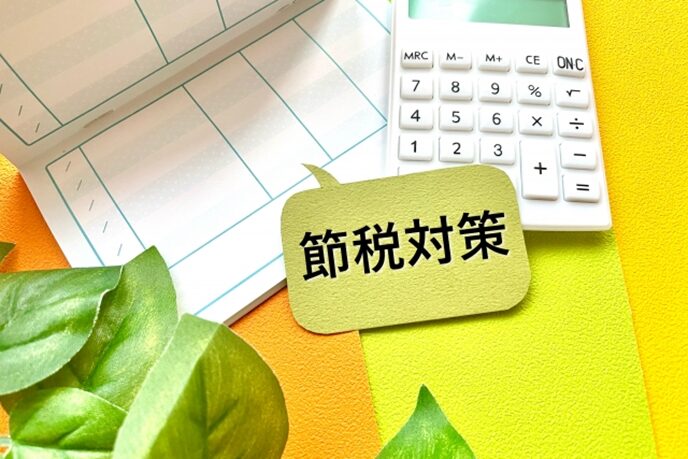
不動産の減価償却とは何か
減価償却とは?その仕組み
減価償却とは、建物などの資産が時間の経過や使用によって徐々に価値を失っていくことを会計上で表現する仕組みです。企業や個人が事業用に資産を購入した場合、その費用を一度に経費として処理するのではなく、使用可能な年数(耐用年数)にわたって分割して計上していきます。
たとえば、1,000万円の建物を購入し、その耐用年数が20年とされた場合、毎年50万円ずつを「減価償却費」として経費にできる、という考え方です。これにより、会計処理がより現実的かつ公平な形になります。
なお、減価償却の対象となるのは建物や設備など、時間とともに不動産価値が下がる資産です。
一方、土地のように通常は価値が下がらない資産については、減価償却の対象外となります。こうした資産は「非減価償却資産」と呼ばれます。
不動産における減価償却の重要性
不動産において減価償却は、単なる会計処理ではなく、節税や投資収益の最適化に直結する重要な要素です。
特に不動産投資を行う場合、建物部分の減価償却費を毎年経費として計上することで、課税所得を圧縮することができ、結果として支払う税金を抑えることが可能になります。
たとえば、不動産収入が年間500万円あったとしても、減価償却費として100万円を計上すれば、課税対象となる所得は400万円に圧縮されます。
これはキャッシュフローを改善し、資産形成を加速させるうえで有効な手段となります。
また、不動産の種類や使用目的によって、適用される減価償却の方法や耐用年数が異なるため、減価償却の制度を正しく理解しておくことが、長期的な不動産の運用を成功に導く鍵となります。
不動産の減価償却の計算方法について解説
ここでは、減価償却の計算方法について解説していきます。
難しいと敬遠されがちですが、計算方法を理解してしまえば今後も減価償却を考える際に活用できるので、概要を確認していきましょう。
定額法による計算方法
定額法は、毎年同じ金額の減価償却費を計上する方法です。
シンプルで分かりやすいため、建物や構築物に広く採用されている計算方法です。
まず、建物の法定耐用年数と償却率をみてみましょう。
こちらは建物の種類ごとの耐用年数と償却率をまとめた表になります。
この数字をもとに、計算を行っていきます。
| 種類 | 事業用 耐用年数 | 償却率 | |
| 建物 | 木造 | 22年 | 0.046 |
| 鉄骨造 (鉄骨の厚みが3mm超4mm以下) | 27年 | 0.038 | |
| 鉄骨造 (鉄骨の厚みが4mm超) | 34年 | 0.030 | |
| RC造(鉄筋コンクリート造) | 47年 | 0.022 | |
| 構築物 | アスファルト舗装、フェンス | 10年 | 0.100 |
| ブロック塀 | 15年 | 0.067 |
<出典>
計算式:減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率
<例>
———–
木造の建築物を購入したとします。
・耐用年数:22年
・償却率0.046
取得価額が1,000万円の場合、毎年の減価償却費は以下のようになります。
1,000万円 × 0.046 = 46万円/年
22年後に、減価償却が完了する計算になります。
———————-
この方法では、初年度から最終年度まで同じ額を経費にできるため、収支の予測がしやすく、安定した会計処理を行いたい場合に適しています。
なお、建物や建物附属設備については、所得税・法人税ともに定額法が法定償却方法とされています。
定率法の計算(平成28年に廃止)
定率法は、平成28年度の税制改正で廃止されていますが、参考程度にご紹介します。
こちらの定率法は、未償却残高に一定の率を乗じて減価償却費を計算する方法です。
初年度に多くの費用を計上し、年を追うごとに減少していくという特徴があります。
計算式:減価償却費 = 未償却残高 × 定率法の償却率
<例>
———–
木造の建築物を購入したとします。
・耐用年数:22年
・償却率0.046
1,000万円 × 0.046 = 46万円
1000万円 – 46万円 =
954万円 × 0.046 = 43.9万円
取得価額が1,000万円の場合、初年度は46万円が償却されます。翌年は、残高954万円に0.046を乗じて、43.9万円が減価償却費になります。
———–
定額法と混同しないよう、知識として知っておくと良いでしょう。
中古不動産の減価償却計算方法
中古不動産の減価償却では、新築とは異なる耐用年数の設定が必要になります。というのも、取得時点である程度の期間が経過しているため、その分を考慮して計算しなければならないからです。
中古物件の耐用年数:減価償却期間 =(法定耐用年数 − 経過年数)+(経過年数 × 20%)
<例①>
———–
木造住宅で、取得時にすでに10年が経過している場合、
・耐用年数:22年
(22年 – 10年)+(10年 × 20%)= 12+2 = 14年
この14年が、新たな耐用年数として使用されます。
———–
さらに、法定耐用年数を超えている不動産を取得した場合でも、20%未満に短縮されることはなく、最低でもその20%が適用されるというルールもあります。
その場合は、該当した法定耐用年数に、一律20%をかけて減価償却期間を算出します。
耐用年数を超えている中古物件の場合:減価償却期間 = 法定耐用年数× 20%
<例②>
———–
木造住宅で、取得時にすでに35年が経過している場合、
・耐用年数:22年
22年× 20% = 4年
———–
こうした独自の計算方式により、中古不動産に対する減価償却費の計上が可能となり、節税メリットを享受できるでしょう。
減価償却を利用、税務上のメリット
減価償却の大きなメリットの一つが「節税効果」です。
不動産投資や法人経営においては、この仕組みをうまく活用することで、課税所得を圧縮し、納税額を抑えることが可能になります。
節税効果とその仕組みを知る
税務上、所得税や法人税は「利益」に対して課税されます。
このとき、減価償却費を毎年の経費として計上すれば、利益(=収入−経費)を圧縮できるため、課税対象額が少なくなり、結果として支払う税金も減るという仕組みです。
たとえば、収入500万円・経費400万円の事業がある場合、利益は100万円です。
しかし、ここに減価償却費が50万円追加されると、利益は50万円に減り、課税額も半分になります。
これは現金の支出を伴わない「見かけ上の費用」であるため、キャッシュフローに影響を与えずに節税ができる点も大きなポイントです。
法人では、定額法・定率法の選択が可能な資産もあるため、業績や資金繰りに応じて、より有利な償却方法を選ぶことで、節税効果を最大化することも可能です。
減価償却費の具体的なメリット例
具体的なケースを見てみましょう。
たとえば、不動産投資家が新築のワンルームマンション(RC造)を2,500万円で購入したとします。このうち建物価格が1,250万円で、法定耐用年数が47年とした場合、年間の減価償却費は約26.6万円となります。
この減価償却費は、実際にお金が出ていく支出ではありませんが、経費として計上できるため、会計上の収益はその分だけ減少します。
仮に、年間家賃収入が108万円、その他経費と金利の合計が72.5万円とすると、減価償却費を含めた経費総額は約99.1万円になります。
この結果、帳簿上の利益はわずか8.9万円にまで圧縮され、課税対象は大幅に減少します。
さらに、初年度に多額の諸経費がかかる場合は、帳簿上の赤字が発生し、給与所得との損益通算が可能です。これによって、所得税や住民税を減額できるため、大きな節税効果が得られるのです。
ただし、こうした節税効果は減価償却期間中に限られ、年数が経過するとともに薄れていくため、長期的な視点での収支バランスも重要になります。
減価償却に関連する注意点
土地と建物の価格分け
減価償却の対象となるのは建物などの「減価償却資産」のみであり、土地は対象外です。そのため、不動産を購入する際には、総額を「土地」と「建物」に明確に分けておく必要があります。
実際には、売買契約書に記載されている土地・建物の内訳を基にしますが、記載がない場合は固定資産税評価額や不動産鑑定評価額などを基に合理的に按分する必要があります。
もし建物部分の価格を過小に設定してしまうと、減価償却費として計上できる額が減り、節税メリットを十分に享受できなくなります。
逆に、建物価格を過大に見積もると、税務署から否認されるリスクもあるため、根拠のある価格配分が求められます。
建物の用途変更に伴う減価償却
建物の用途が変わった場合には、その用途に応じて新たな耐用年数や償却方法を再設定する必要があります。
たとえば、居住用の住宅を事務所として使用する場合、住宅用として設定された耐用年数ではなく、事務所用の耐用年数を使って減価償却を計算し直さなければなりません。
このような変更がある場合には、税理士や専門家と相談のうえ、正しい処理を行いましょう。不適切な償却処理は、後々の税務調査で指摘を受け、追徴課税となる可能性もあるので、注意が必要です。
よくある質問
Q1. 減価償却は必ず行う必要がありますか?
A. 個人事業主や不動産投資家の場合、減価償却は義務です。法人の場合は任意ですが、節税やキャッシュフローの安定化という観点から、実施を推奨されるケースが多いです。
Q2. 建物価格が分からないときはどうすればいいですか?
A. 固定資産税評価証明書や路線価、売買契約書の付属資料をもとに、合理的に土地・建物の内訳を見積もる必要があります。正確な配分が求められるため、税理士のサポートを受けると安心です。
Q3. 減価償却の対象は建物だけですか?
A. 建物だけでなく、エアコンや給湯器、内装工事などの建物附属設備や構築物も減価償却の対象になります。これらは建物とは別の耐用年数や償却方法が適用されるため、個別に管理・計上する必要があります。
まとめ
不動産の減価償却は、単なる会計処理ではなく、適切に活用することで大きな節税効果を生む仕組みです。特に建物部分は経費として計上でき、毎年の課税所得を抑える効果を得られます。
法人・個人を問わず、不動産を保有している場合には、減価償却の方法やメリットを理解し、正確に適用することが求められます。
一方で、土地は減価償却できないことや、建物用途の変更、会計処理上の注意点など、見落としやすいポイントもあります。減価償却の基本を押さえ、専門家のアドバイスも活用しながら、賢く不動産を管理・運用していきましょう。
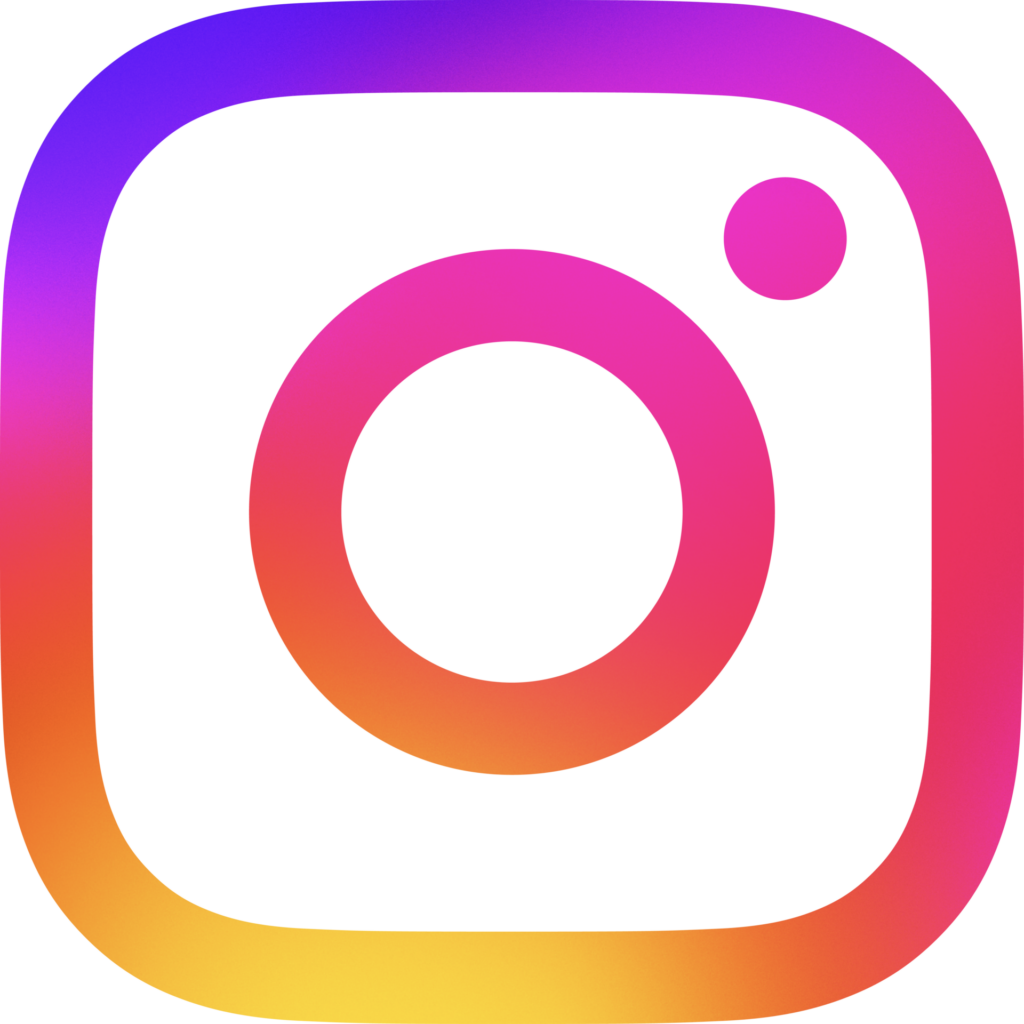
知って楽しい久喜 公式Instagram
久喜の住み心地やタウン情報を発信中!
地域の魅力を身近な目線でお届けします!
【知って楽しい久喜】すまいの相談窓口infoとは
久喜市の不動産会社 株式会社フジハウジングが運営する、不動産解決事例や久喜の情報を発信しているタウンメディアです。
フジハウジングでは、お客様のニーズに合わせたご提案を行い、不動産を通じた人生設計を応援しています。お部屋探し・テナント探し・アパートなどの賃貸管理・資産価値リフォーム・おうち探し・土地探し・不動産のご売却・不動産相続対策・有効活用など、トータルに解決出来るプロ集団ですので、是非お気軽にご相談ください!







