2025年6月発行 広報くきの久喜歴史だよりを転載します。
国指定重要無形民俗文化財の鷲宮催馬楽神楽が奏演される舞台は、神楽殿と呼ばれています。鷲宮神社の神楽殿は、今から約200年前の文政4年(1821)に建てられました。神楽殿は本殿に向かいあって建てられており、神楽を祭神にご覧いただけるよう配慮がなされているといえます。
神楽殿は、入母屋造り、三方吹き抜けで、鏡板には日の丸に松が描かれています。間口3間(約5m40㎝)、奥行2間半(約4m50㎝)を舞台とし、その奥に3尺(約90㎝)の囃子座があります。また、向かって左に間口1間半(約2m70㎝)、奥行1間(約1m80㎝)の橋掛りがあります。
神楽殿再建の経緯を記した棟札によると、享保11年(1726)に再建された神楽殿が年を経て破損が甚だしいので、これを嘆いた八甫村の渡辺七左衛門、下新井村の青木勘左衛門・本田元右衛門・同由右衛門らが中心となり、講中の助成を受けて修理料を集めたこと。これを受け神主大内国義が文政4年10月に竣工・上棟の神事を行い、同年11月に神楽殿を再建したこと。大工棟梁は川口村(現加須市)の嶋田善六・木挽棟梁は鷲宮村の小森忠兵衛・屋根棟梁は鷲宮村の高橋佐七であったことが分かります。
その後神楽殿は、約100年後の大正13年(1924)に屋根が葺き替えられ、草葺から亜鉛鉄板葺になりました。また、昭和50年(1975)4月には、屋根を修繕し、コールタールが塗布され、さらに昭和54年(1979)10月には、屋根を葺き替え、亜鉛鉄板葺から銅板葺になりました。しかし文政4年の再建から約200年後の今日、神楽殿は老朽化が著しく、耐震化の対応が急務となったことから、令和7年度と令和8年度の2カ年度にかけて耐震補強・保存維持工事を行うことになりました。工事期間中は、鷲宮催馬楽神楽は鷲宮神社に設けた仮設の舞台で奏演されます。神楽が再び神楽殿で舞われるのが今から待ち遠しいですね。
文化振興課文化財・歴史資料係(内線362)
出典
出典・リンク:広報くき 令和7年6月号 P4-5
まとめ
今回は久喜歴史だよりより「鷲宮神社の神楽殿と鷲宮催馬楽神楽(さいばらかぐら)」についてご紹介しました。
神楽殿は今からおよそ200年前、文政4年(1821)に再建された歴史ある建物で、神様に神楽を捧げる特別な舞台として親しまれてきました。
これまで何度も修繕が行われながら、地域の人々に大切に守られてきた神楽殿も、今では老朽化が進み、いよいよ大規模な保存工事が行われることになりました。
工事の間、神楽は仮設の舞台で披露されるそうですが、また神楽殿で舞が披露される日が楽しみですね。
鷲宮神社を訪れた際は、ぜひこの神楽殿にも注目してみてください。
久喜市郷土資料館では、こうした地域の歴史文化についても詳しく紹介されていますよ。
今後も久喜歴史だよりをお届けしていきますので、どうぞお楽しみに♪
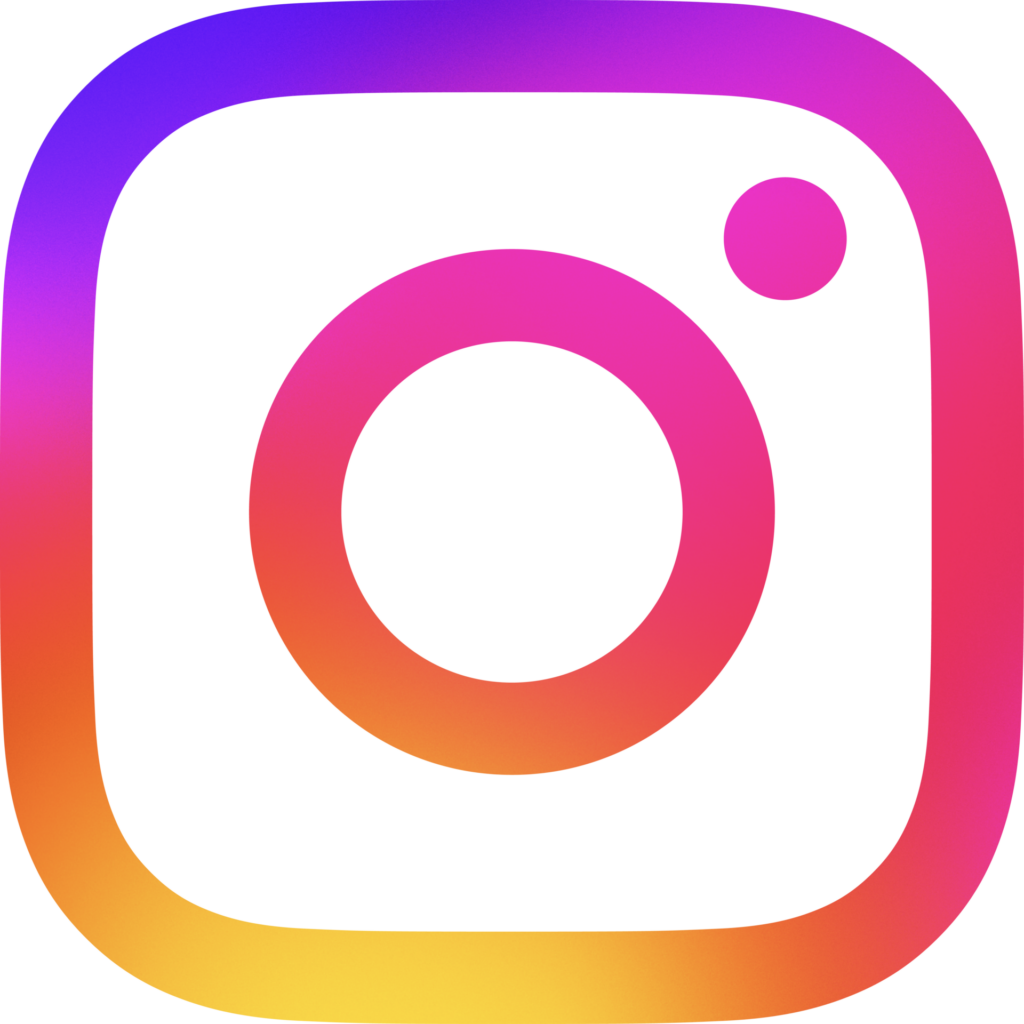
知って楽しい久喜 公式Instagram
久喜の住み心地やタウン情報を発信中!
地域の魅力を身近な目線でお届けします!
【知って楽しい久喜】すまいの相談窓口infoとは
久喜市の不動産会社 株式会社フジハウジングが運営する、不動産解決事例や久喜の情報を発信しているタウンメディアです。
フジハウジングでは、お客様のニーズに合わせたご提案を行い、不動産を通じた人生設計を応援しています。お部屋探し・テナント探し・アパートなどの賃貸管理・資産価値リフォーム・おうち探し・土地探し・不動産のご売却・不動産相続対策・有効活用など、トータルに解決出来るプロ集団ですので、是非お気軽にご相談ください!







