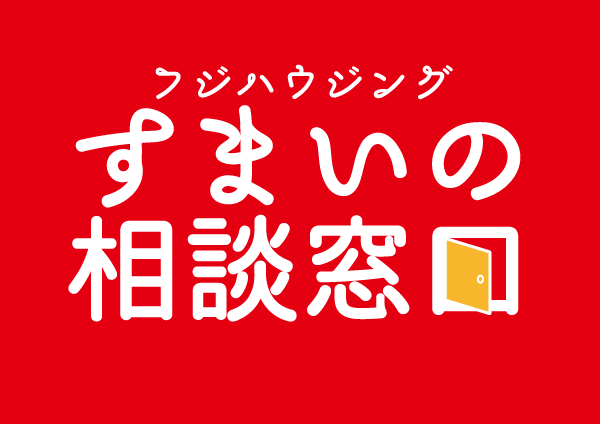2025年1月発行 広報くきの久喜歴史だよりを転載いたします。
戦前の教育界の最前線 教育記者 相澤熈(あいざわひろし)
相澤熈は明治13年(1880)に葛梅村(現久喜市葛梅(くずめ))に生まれ、幼少期は鷲宮尋常小学校に通いました。その後、英語専修学校(現在の立教大学)を卒業した後、明治43年の東京万国博覧会で通訳をしていたときに徳富蘇峰(とくとみそほう)と出会い、蘇峰が社長を務める国民新聞社に入社することになりました。国民新聞社では文部省の担当記者となり、以後教育問題を専門とする教育記者として活躍しました。大正8年(1919)には国民新聞一万部発行記念事業として国民教育奨励会が創立され、熈は専務理事として教師の講習会や教育図書の発行等に尽力しました。また、昭和2年(1927)には全米教育会議や万国教育連合総会などの国際的な会議に日本の代表の一人として出席し、世界を舞台に活躍しています。
昭和4年に蘇峰が国民新聞社を離れる事態に陥(おちい)った際、熈は蘇峰と共に退社し、昭和9年には国民教育奨励会からも退くことになりますが、その後も昭和10年に東京で開かれた汎(はん)太平洋国際会議で事務総長を務め、帝国教育などの団体役員を複数務めるなど、教育界の最前線で活躍しました。こうした熈の教育界における活躍は周囲からも高く評価され、昭和15年に開かれた「相沢熈君教育者三十年功労感謝会」では、文部大臣経験者など200名が参加し、熈の功績をたたえています。

しかし、昭和18年に太平洋戦争が激化すると、熈は全ての役職から身を引き、昭和20年には故郷の鷲宮に疎開して終戦を迎えました。その後、鷲宮神社の宮司であった甥(おい)の招きで鷲宮神社の社務所に拠点を移し、師である蘇峰のことや教育史等を執筆して過ごしました。また、「清和会」(せいわかい)という会合を開き、熈を慕って集まった地域の有識者と時事問題について語り合うこともありました。その後、昭29年に久喜に転居し、昭和31年に77歳で生涯を閉じました。
相澤熈は自身を「街頭の教育者」と表現しています。これは、教育記者とは教育の現場に立つ教育者ではないが、文筆を通して人を教育する教育者でなければならないという信念を表しており、日本の教育のために記事を書き続けた一生がそれを物語っています。
問合せ 久喜市立郷土資料館 ☎0480-57-1200
出典
出典:広報くき 令和7年1月号
リンク:https://www.city.kuki.lg.jp/shisei/koho/kuki/kohokuki_r07/koho202501.files/b_16-17.pdf
まとめ
今回は久喜歴史だよりの「戦前の教育界の最前線 教育記者 相澤熈(あいざわひろし)」を紹介しました。
30代の相澤熈が国民新聞社の社長を務める徳富蘇峰と出会い、どんな影響を受けて教育記者の道に進んだのでしょうか。
当ホームページでは久喜市郷土資料館について過去の記事で紹介しています。そちらもチェックして久喜市郷土資料館に訪れてみるのもいいですね。
今後も久喜歴史だよりを転載していきます。お楽しみに♪